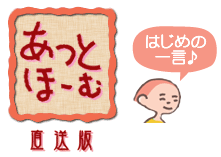
センターの一日は、ご利用者の到着とほぼ同時に来園され、声かけしながらお迎えして下さるボランティアさんの心地よい支援で始まります。園内のどの場面で も、自然体でご利用者に寄り添う語りかけは、ご利用者だけでなく、職員までも和ませて下さり、学ぶ事が多い存在となっております。「感謝の集い」は、心か らの感謝をささやかながら形として表す一日です。 ケアセンターサービスマネージャー 深宮美佐子
平成18年6月号
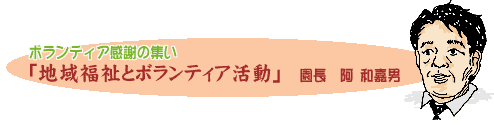
ボランティアの皆様の日々の活動に緑寿園はこころから感謝いたしております。
高齢のご利用者一人一人に丁寧なおもてなしをしていただくこと、入浴、アクティビティ活動、絵画・陶芸、語らいの時間等など活動と活動後の始末までも、き れいに付けてくださること。花を飾り、庭を気持ちよく整えていただくこと、心を込めた気配りと目の配りが、安らいだ時間を作り出していただいています。緑
寿園のボランティア活動は、長い歴史を持っています。奉仕活動と総称されていた時代から、ボランティア活動へ、その根源の精神は変わりません。人が様々な 障害をもちながらも、安らかで豊かに日々の生活を営み、人として穏やかな終末を迎えることが出来るように、日々の生活が粗末でなく、丁寧で木目の細かな思
いやりによって満ちているように願い、活動する姿は見事です。その一つ、緑寿園4階北東にあるランドリーでは、見事に糸くず一つ残さない和やかでピシッと した活動が長く続いています。緑寿園のテーマの一つは「0から100まで」、ボランティアの皆様も様々な世代の方がいらして、活動場所も活動内容もそれぞ れですが、当たり前のように親しい言葉が交わされています。
最近になって特に地域の再生が強調されていますが、高度経済成長とともに、長い時間をかけて醸成されたそれぞれの地域文化が拡散されてしまい、一つ一つの 過程が小さなカプセルのようになって、日々の生活の中で捉える時間を短くしてしまいました。緑寿園は、長い時間を見据えてこの地域を育てていく活動をボラ ンティアの皆様と共有していきます。
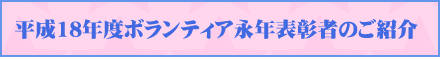
~20年表彰者~
田家 榮子 様 「手芸・喫茶のお手伝い」
利用者の皆様に喜んでいただける事や、自分を待っていてくれる人がいる事に生き甲斐を感じております。手芸は奥が深く工夫次第で楽しい作品が手軽にできます。これから、もっと勉強して皆様のお役に立てれば幸いです。
磯辺 照美 様 「リズム運動の指導」
緑寿園は園全体が家庭的な雰囲気で活動しやすいところです。リズム運動でのみなさんの笑顔に支えられ、また自分自身の健康維持のため、今後も楽しく続けていただけたらと思います。
~10年表彰者~
松本 君枝 様 「組紐作りのお手伝い」
榎本 秀子 様 「朗読・喫茶・入浴のお手伝い」
柏木 節子 様 「喫茶のお手伝い」
橋本 カナ子 様 「認知症デイサービスでのお手伝い」
長谷川 京子 様 「手芸のお手伝い」
近藤 京子 様 「ランドリーでのお手伝い」
篠原 美代子 様 「認知症デイサービスでのお手伝い」
中山 セキ 様 「整髪・手芸のお手伝い」
黒崎 祐子 様 「認知症デイサービスでのお手伝い」
その他2名様
以上13名の方が5月31日ボランティア感謝の集いの席で理事長表彰されました。
昨年度は、延べ人数にして約4600名の方が、ボランティア活動をされています。緑寿園では、長い間活動されている方が多く、個人登録されている方の活動 平均年数は、約8年にもなります。この年数は私達の大変貴重な財産であり、誇りに思える数字と自負しております。ボランティアさんなくして緑寿園の活動は 考えられません。ただただ感謝です。これからも、益々活動を続けて頂けますようお願いいたします。
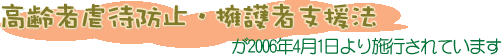
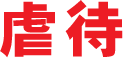
この法律は、「児童虐待防止法」、「配偶者暴力防止法」に続いてできた人権擁護に関わる法律です。高齢になった時、誰でも尊厳を持って暮らしたいと望んでいます。・・・でも現実には必ずしもそうはいかないことがあります。
この法律は、早期発見・早期対応するために高齢者虐待に[疑いも含めて]気づいた方は、市役所にある福祉の事務所や地域包括支援センターへご一報くださいとうたっています。
とても特別なことのように思います。・・・でも現実には・・・。
虐待をしている人もされている人でさえも虐待だと意識していないことの方が多いのが実情です。
例えば・・・
転んで骨折したら大変と車椅子から立ち上がれないようにしているとしたら・・・?
本人にとっては自由を奪われ身体機能の低下を招いていることになります。
何度も同じ事を繰り返して!叱責することで・・・本人は“もういなくなったほうがよい”と辛い思いを募らせ心が深く傷ついているかもしれません。
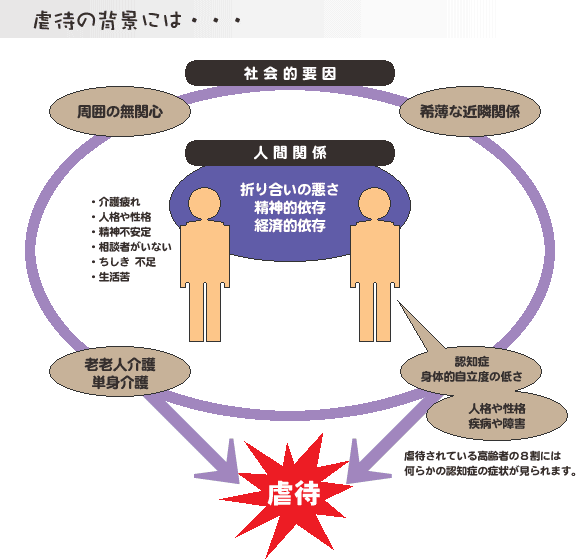
虐待は特別な家庭に起きているということではなく、種々の要素が重なった時、どこの家庭でも起こりうる身近なこととして認識する必要があります。
こんなことに気づいたら・・・虐待のサインは!!
身体に複数のあざ、頻繁なあざ。あざや傷についての説明がつじつまが合わない。隠す。
おびえた表情、急に不安がる、家族がいるといないとでは態度が異なる。
関係者に話すことを躊躇する。話す内容が変化する。新たなサービスは拒否する。
いつも汚れたままの服装をしている。身体の異臭、のび放題の爪。
痩せが目立つ。よそではがつがつ食べる。
話したがらない、自分を否定的に話す、「ホームに入りたくない」「死にたい」などの発言。
「お金をとられた」「年金が入ってこない」「貯金が無くなった」などの発言。
資産と日常生活の落差。
擁護者の高齢者に対する態度が冷淡、横柄、無関心、支配的、攻撃的、拒否的。
生命身体に重大な危険が及んでいると思われる場合は通報する義務があります。
そうすることで虐待を受けている人も虐待をしている人も救われる可能性があります。
